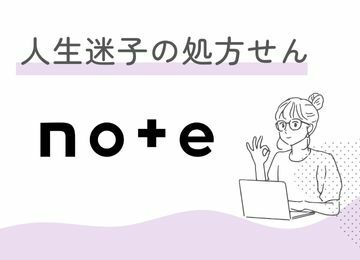- ホーム
- 女性のための人間力アップ講座(全15回)
- 女性のための人間力アップ講座
- 女性の人間力アップ講座【第5回】わが子の教育
女性の人間力アップ講座【第5回】わが子の教育

今回のテーマは「わが子の教育」
「わが子の教育って言われても、私、子どもはいないんですけど。。」という方もいらっしゃると思います。私もその1人。
でも人を育てることは、部下やスタッフ、また生徒、受講者など家庭以外にも様々な場面で遭遇しますよね。
本質的には、大切なことは共通している。
ということで、それぞれの立場で、どう生かせるか考えてもらいながら読んでもらえると嬉しいです。
ではでは、今回は森先生が教える「教育の5つの心得」にまとめてみました。
それではいきましょう!
心得その1:教育の心構え・資格は「1日にしてならず」と心得る
「わが子を教育する」ということは、実は十年後にわが子をもって初めて始まることではないからです。(中略)「ローマは1日にして成らず」とか、すべての事の成るのは、成る日に成るのではないということを聞いておられるでしょう。…すなわち現在のあなた方の日々の生活が、実はそのまま十年後の母としての心構えと資格とを、一つづつ積みつつあるともいえるからであります。
約10年前、若者の就労支援施設でキャリアコンサルタントとしてデビューした時に、先輩カウンセラーから受けたアドバイスでこんな言葉がありました。
「阿部さん、何を言うのか、よりも、誰が言うかが大事なんだよ」
この言葉は強く印象に残っていて、今でも時折思い出してわが身を振り返り、反省。。。をするんですが、「何が」よりも「誰が」が結局重要なんですよね。
これは結局、いい人材を育てていくには、その場になってすぐできるものではなくて、その人の在り方の積み重ねが重要。
あー、やはり日々の鍛錬・身を修めることに向き合わないといけないってことですね。
心得その2:わが子は所有物ではない
平素ともすればわが子を、自分たち夫妻の所有物でもあるかに考えやすいのですが、しかしその誤りについては、ただ今申したことによってお分かりになられたことでしょう。同時にこの点がよくわからないと、あるいは溺愛に陥り、あるいは過酷に失するということにもなるわけです。
わが子とはいいながら、実は何ら私すべきものではないということが、わかるはずであります。仏教でしたらこれを「仏の子」と言うのでしょう。
学生さんのキャリア相談を受けていると、親の影響力が強くて苦しんでいる学生さんにお会いします。彼ら、彼女たちは親のことは大好きなのに、自分たちの想いと違うことに悩んで、涙ながらにその思いをぶちまけることがあるんですよね。この時は話を聞いているこちらもつらい。。親と子の距離感の取り方って、近しいからこそ難しいよなあ、とホントに思います。
また、親としての子どもの関わり方だけでなく、指導育成をする側としても、ついつい自分の思い通りにしたくなるもの。思うとおりに動いてくれなかったり、成長がみられないと、イライラなんてことも。。
人間は神の子といった表現をされることもありますが、子どもであれ、自分とはまったく違う存在である。というもう一人の自分がいるような、第三者的な視点を持つことが大切、ってことですね。
心得その3:天から受けた天分を十分に発揮・実現できるように育てる
天からう受けた天分ってどう見つけるの?と思いますよね!
それに関しては、2つの方法を教えてくださっています。
1つ目
結局はわが子が「好き」ということをもって、一応わが子の天分の「芽生え」とでも考えるほかないでしょう。
とにかく好きから入れ!ってことです。でも、好きで始めても才能がなかった、なんていうこともあります。その場合は、それに気づいた時がタイミング。とにかく一応は好きから初めて、やってみてからまた考えましょう。とアドバイスくださってます。
そして2つ目は、好きからスタートして、ある程度の地点まで来た後の対応。改めて天分に迷ったときにオススメされているのが消極駅選択法(ネガディブセレクション)という方法です。
自分のいくつかの希望を並べてみて、自分の自信がないものから消していくというもの。自分で「これはダメ」と思われるものから順に消していくと最後に1つ残る。そもそも自分としては自信があるわけではないが、でももうそれ以外ないとしたら、それを選ぶしかなーい!といった選び方ですね。
このネガティブセレクション。消極的と思われるかもしれませんが、やりたいことが見つからない時にも活用できます。進路や方向性に迷った時の1つの考え方として、ぜひ参考にしてみてくださいね!
心得4:やりぬく人間に育てる
はい、そして4つ目ですが、
わが子の天分の発揮いう点でより大事な問題は、自分の志した事項はあくまでこれをやり抜くという、堅忍不抜の精神のタネ蒔きをすることだといってよいでしょう
堅忍不抜とは、どんなつらいことがあっても、心を動かさずにじっと耐えること。我慢強いこと。
我慢強さって、現代人が苦手なことの一つですよねー(もちろん私もですが)
できれば嫌なことはやりたくないし、つらいことも我慢はしたくない~。でも、そんな悪魔のささやきと葛藤しながらも、やり抜かなきゃいけない時は、やらなきゃいかん!のですよね。人生は。
で、そのやり抜く力をつけるための方法も森先生は教えてくださっているんですよ~。それがこちら!
(教育上の)一番根本的と考えることをそれを何かと言うに、結局四六時中「腰骨」を立てて曲げない子どもにするということでありまして、これこそは、人間として一番根本的な問題といってよいでしょう。
腰骨を立てる!これが我慢強さを育むコツだそうです。腰骨を立てる、とはどんな姿勢かというと、こんな感じ。

①お尻をウンと後ろに引く
②次にお尻のやや上の方の腰骨をできるだけ前方へ突き出すという姿勢ですね。こんな姿勢になっていたら、

「おっと!腰骨腰骨!」と体勢を整えていきましょう笑
心得5:人に対して親切な人間に育てる
そして最後5つめの心得です。なぜ親切が大切かというと、
われわれ人間というものは、たとえその人がいかに才知才能があったとしても、もしその人間が利己的であって、何ら人のために尽くすことがなかったとしたら、それは実につまらない人間であって、わたくしたちはそういう人間に対しては、何ら尊敬の念が持てないどころか、なまじいに才能があるがゆえに、かえってそういう人間に対しては、心中ひそかに軽蔑せずにはいられないでしょう。
いくら才能があっても自分勝手な人に対しては、表面では褒めちぎりながらも、心の中では「この人サイテー!」なんて気持ちがむくむくと、、、なんてことは実際にありますね笑 人に言われなくても、周りへの気遣いができるかどうか。これは、人として誰もが大切なこと。自分がそうなっていないか、、振り返りチェックです!
最後に
今回はわが子の教育として次の5つの心得をピックアップしました。
- 心得1:教育は「1日にしてならず」と心得る
- 心得2:わが子は所有物ではない
- 心得3:天から受けた天分を十分に発揮・実現できるように育てる
- 心得4:やりぬく人間に育てる
- 心得5:人に対して親切な人間に育てる
この講義の最後に、これを実現するためには、まずは教育する側がいったん決心したことは必ずやり抜く気持ちを持って、自分自身が実行することがその一歩です。としめくくられています。
どれも当たり前、というようなことですが、これをやり抜くって、そうそう簡単ではないんですよね。。
その中でも今、すぐにできることといったら「腰骨を立てる」ことではないでしょうか。この姿勢で座っていたら、スッと背筋が伸びていて、見た目もカッコイイ。女子力アップも間違いなし笑
結局教育する側って、「お前に言われたくないよ!」と言われないようにするのも大切ですし、カッコ良さもとても大事だと思うんですよね。まずは座っている時には足を組んだりせずに腰骨を立てて座る。これ、ぜひやっていきましょう!